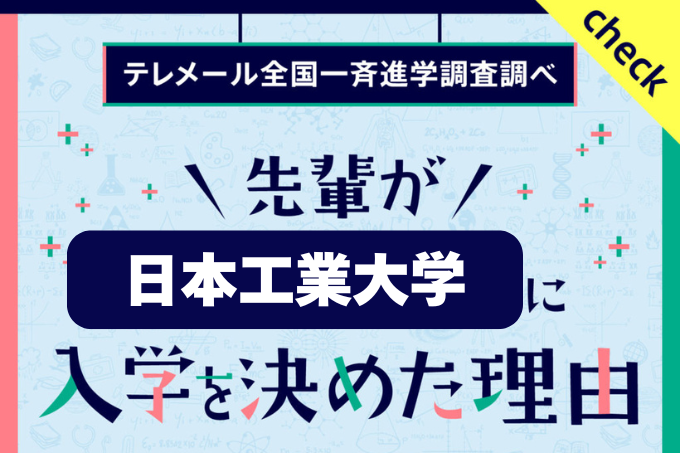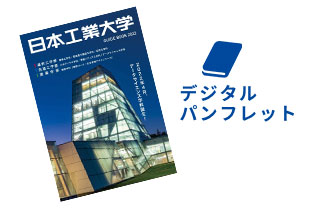WELCOME TO NIT!
日本工業大学を知る第一歩は、このページから。
We do have!

立地と通学
埼玉キャンパスは、南埼玉郡宮代町の閑静な住宅地にキャンパスがあります。
大宮駅などの都市圏や東京都にも近く、アクセスの良さが大きな特徴。
最寄り駅である東武動物公園駅からの通学路には、学生生活が 捗る商業施設があり、一人暮らしにもとても適した環境です。
学びの特色
開学から一貫している「実工学の理念」に基づき、
充実の工学教育と先進的研究による学修を展開しています。
学部・学科
幅広い工学を学ぶことのできる
3学部7学科2コース体制。
最先端の確かな専門力と、
豊かな人間性を育みます。

充実した施設
日本工大には、学生生活を彩るための施設やセンターが充実しています。
ここではその一部をご紹介します。
「ラーニングキューブ」
多目的講義棟「ラーニングキューブ」
2018年12月に竣工した多目的講義棟「ラーニング・キューブ」。地上7階建の校舎は日本工大のランドマークです。大小様々な教室や学生が自由に使える学修スペース、学生を支援するサポートセンターの他、1階には購買 (コンビニ)やブックカフェも備わっています。
LCセンター(図書館)
LCセンターは、学園創立100周年を記念して建設されたことから「百年記念館」とも呼ばれています。学術研究施設として20万冊を超える豊富な図書や文献を備え、インターネットやパソコンも多数整備しています。
LCセンター詳細
学修支援センター
誰もが自由に利用できる自修室です。学業サポートのほか、大学生活や人間関係についての悩みといった、学生 一人ひとりの相談にも専門スタッフが対応します。
学修支援センター詳細
英語学習サポートセンター
英語コミュニケーション能力を向上させ、異文化・多文化環境に立ち向かえる意識と能力を身に付けるための資格取得支援や多様なプログラムを用意しています。外国人講師がセンターのスタッフとして常駐しています。
英語学習サポートセンター詳細
教職教育センター
教職課程履修学生と、教員を志す学生を支援しています。また、各県の教員採用試験情報の収集や非常勤講師、常勤講師などの求人紹介等の支援も行っています。
教職教育センター詳細
スチューデントラボ
個人でも友達同士でも、いつでも自由にものづくりに打ち込めるスチューデントラボ。工作機械や道具も利用できます。
スチューデントラボ詳細
インテリアデザインラボ
工作機械や家具組立のスペースを備えており、家具製作実習を行うことができる工房です。
インテリアデザインラボ詳細
ダイニングホール
2017年にグランドオープンした、1,000名を収容できる大型食堂です。日替わりランチ(390円)や麺類(180円 〜)が人気で、寿司コーナーやベーカリコーナー等もあり多くの学生が利用します。美味しい食事を囲みながら、 仲間と楽しい時間が過ごせます。
ダイニングホール詳細
キッチン&カフェ トレビ
六角形の屋根がスタイリッシュな建物で、開放的なテラス席が目印。パスタ(380円〜)やドリア(350円〜)などのイタリアンが絶品です。
キッチン&カフェ トレビ詳細
レストランアルテリーベ
モーニングからランチ、ティータイムまで豊富なメニューがそろっています。落ち着いた雰囲気の中で、ゆっくりと食事やお茶が楽しめます。
レストランアルテリーベ詳細
スチューデントホール
授業以外の時間に多くの学生が集まる人気施設。お昼にはカレーの販売、地下には「防音スタジオ」が整備されており、部活やサークルで利用されています。
スチューデントホール詳細
クラブ棟・各種運動施設
部室や会議室、シャワー室を完備したクラブ棟や、部活動やサークル活動を行う施設の他、体育館にはウェイト トレーニングマシンなどを完備したトレーニングルームがあります。
センターの詳しい紹介や、その他の施設についてはこちら
就職に強い
幅広い就職先や、確かな就職実績、手厚いサポート体制で
学生の就職活動を支援します。
就職率 %
(2024年度卒業生)
求人倍率 倍!
(全国平均1.2倍)
主な就職内定先
メーカー系
HONDA(本田技研工業)、日産自動車、SUBARU、三菱自動車工業、日立製作所、伊藤園、クラレ、JFEスチール、アイリスオーヤマ、オムロン、SMC、オリンパス、曙ブレーキ工業、日立Astemo、ミネベアミツミ、富士電機、能美防災など
インフラ・建設
JR(東日本/東海/西日本/貨物)、東京メトロ、東京電力ホールディングス、大林組、清水建設、積水ハウス、大和ハウス工業、ポラス、NTTファシリティーズ、関東電気保安協会、大和ハウス工業、きんでん、関電工、五洋建設、長谷工コーポレーション、ヒノキヤグループ、三井住友建設、熊谷組など
ソフトウェア・通信
NTTドコモ、ソフトバンク、NTT東日本グループ、カプコン、富士通、サイバーエージェント、東芝システムテクノロジー、Freee、NECネッツエスアイ、NTTデータグループ、日立システムズ、電通クリエーティブキューブ、大和総研インフォメーションシステムズ、富士フイルムビジネスイノベーションジャパンなど
官公庁等ソフトウェア・通信
総務省、埼玉県庁、教育委員会(東京都、埼玉県、他)、警視庁、東京都庁、群馬県庁、福島県庁、教員(中学校)、教員(高校)など